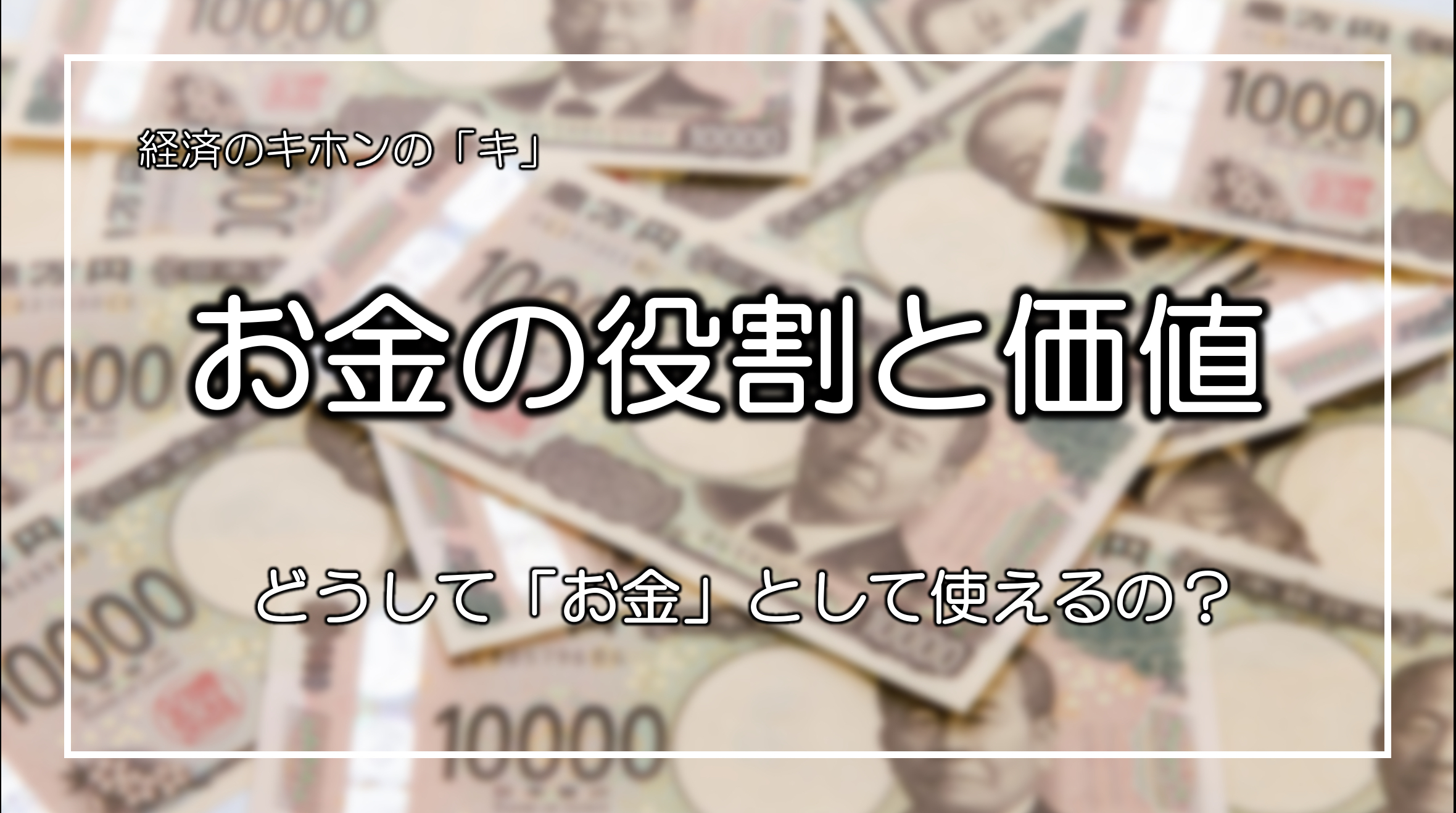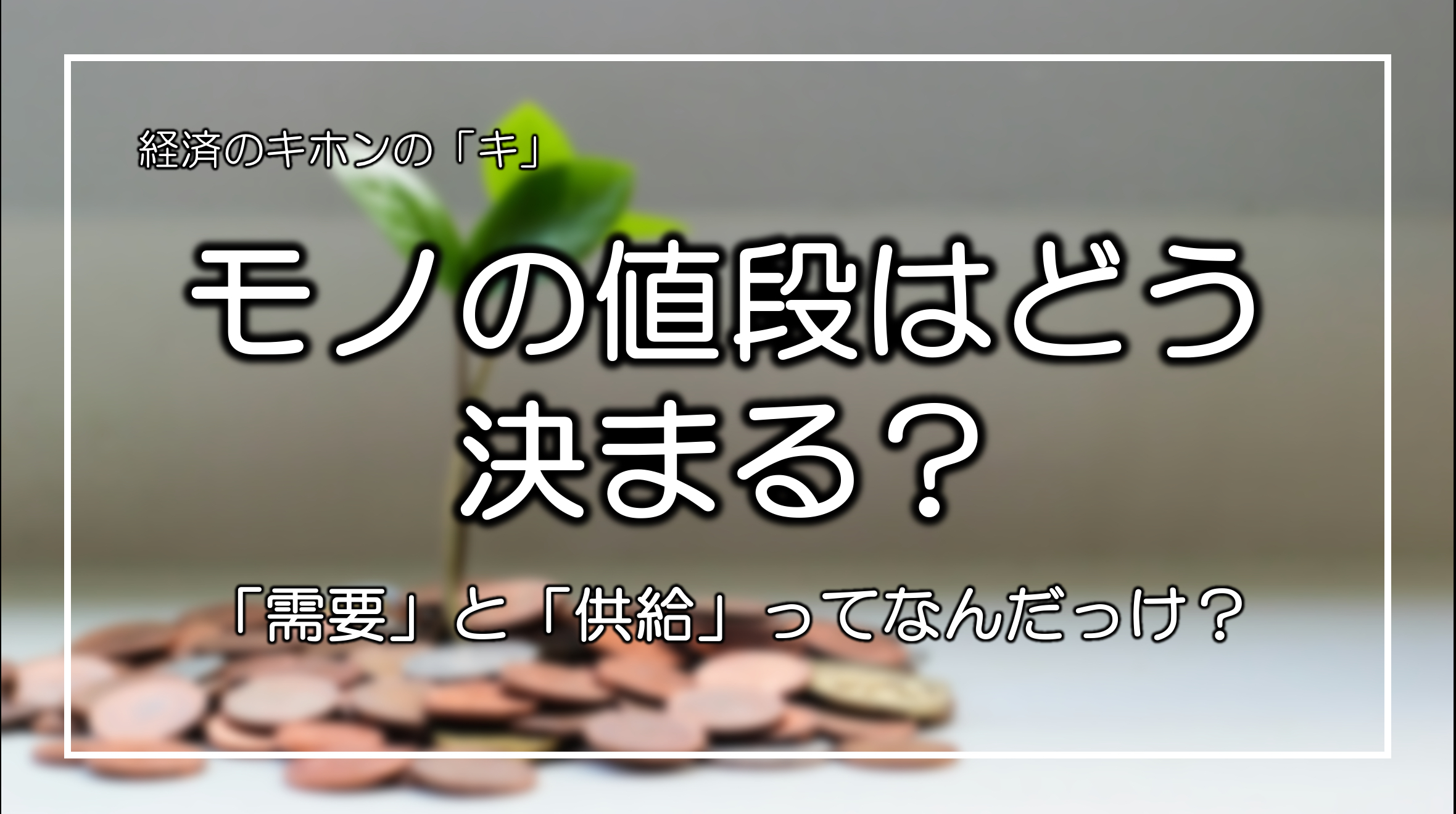みなさん、財布の中をのぞいてみてください。
1万円札が入っていたら「おぉ、今日は勝ち組!」って気分になるかもしれません。
でも冷静に考えると、ただの紙切れです。印刷のインク代を考えたら数十円レベル。
じゃあなんで私たちはその紙切れでご飯を食べられるのか?
今回は「お金ってなんなの?」を解説します。
この記事のまとめ
- お金には「交換手段」「価値のものさし」「価値の保存」という3つの機能がある
- お金の価値は「信用」によって成り立っている
- 信用があるからこそ、経済はお金を介してスムーズに動く
お金の3つの機能
お金には3つの超重要ミッションが与えられています。
- 交換手段(支払い便利グッズ)
- 「リンゴ3個と魚2匹、交換しよ!」みたいな物々交換は、時代劇の村祭りならともかく現代社会には向いてません。
- そこで登場するのがお金。スーパーで「1万円で」って言ったらリンゴでも魚でもすぐ手に入る。
- 価値のものさし(共通のメジャー)
- リンゴと魚を比べるとき、「どっちがどれくらい価値ある?」って考えるの面倒ですよね。
- でも「リンゴ1個=100円、魚1匹=500円」って言われれば一瞬で理解できます。お金は経済の翻訳アプリです。
- 価値の保存(お金は腐らない)
- お金は腐らないし、賞味期限切れもありません。
- 「今日働いて稼いだ1万円」を来年まで持ち越してもちゃんと1万円。冷蔵庫いらずで保存可能。
お金の価値は「信用」で決まる
お金の正体は紙や数字。でも、それに価値が宿るのは「みんなが使うと信じているから」です。
「一万円札」と「魚」の価値について比較してみましょう。

たとえば、もしあなたが無人島に流れ着いた場合。 どっちが役に立つでしょうか?
もちろん魚です。 魚は今日の夕飯になりますが、1万円札は焚き火の着火剤にしかなりません。
「一万円札」の物質的な価値なんてそんなもんです。
逆に街に戻れば、魚を持ち歩くよりも一万円札のほうが圧倒的に便利。
「この紙には一万円分の価値がある」とみんなが合意しているので、「一万円札」は一万円分の価値を発揮します。
つまりお金の力は、「物理的な価値」じゃなくて「社会全体で共有している認識」によって生まれています。
言い換えれば、お金は “みんなの合意” によって成立しているんですね。
信用が経済を回す
お金は、経済の「潤滑油」のような存在です。
信用によって価値が保たれ、それが3つの機能を果たすことで、人々は安心して取引や投資、貯蓄ができます。
逆に、この信用が揺らぐと、経済全体がぎくしゃくし、取引や投資が止まってしまいます。
まとめ
次に財布からお札を取り出すとき、ぜひ「これはただの紙だけど、みんなが信じているから使えるんだ」という視点で見てみてください。
きっと、お金に対する見方が少し変わるはずです。