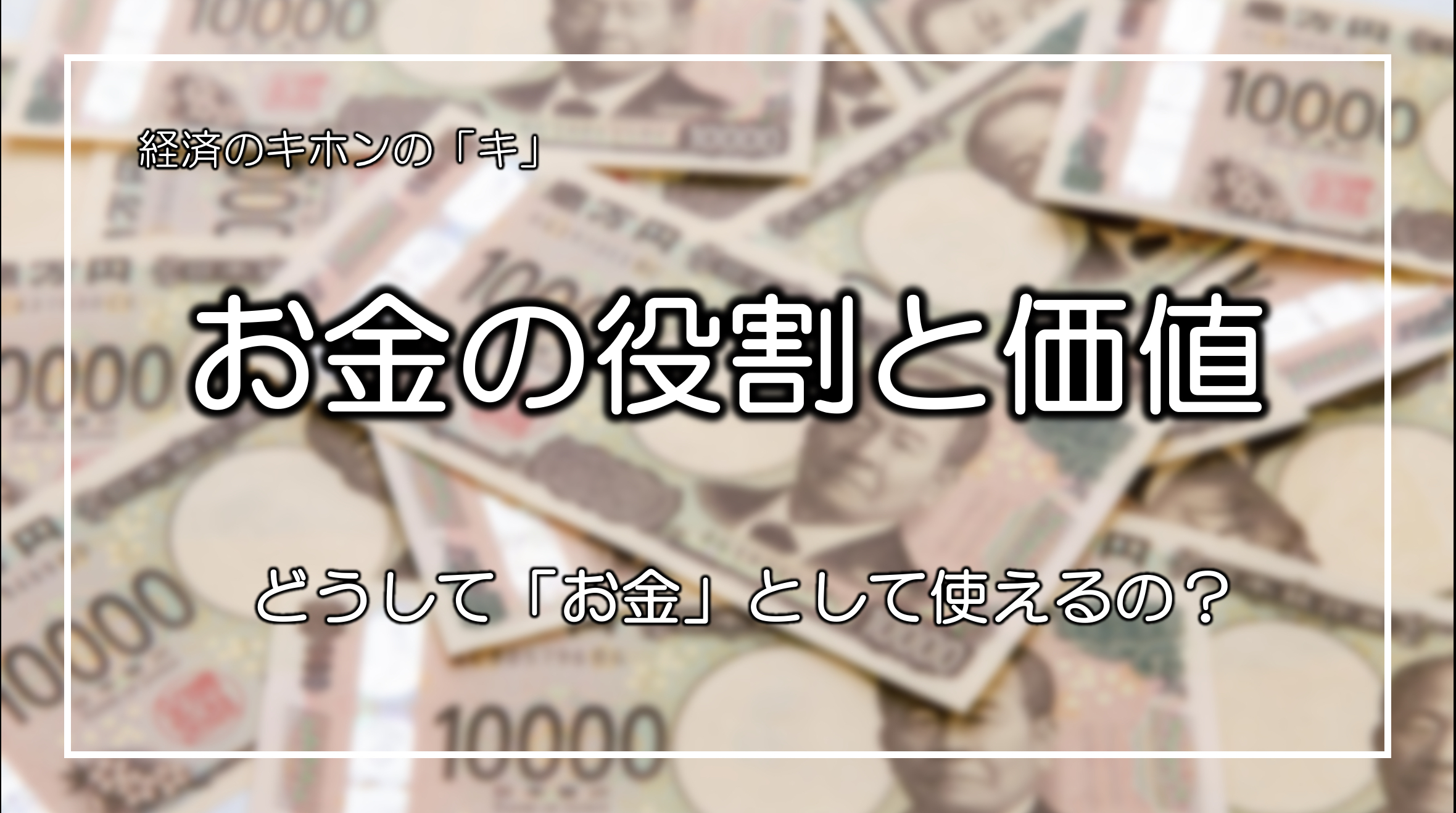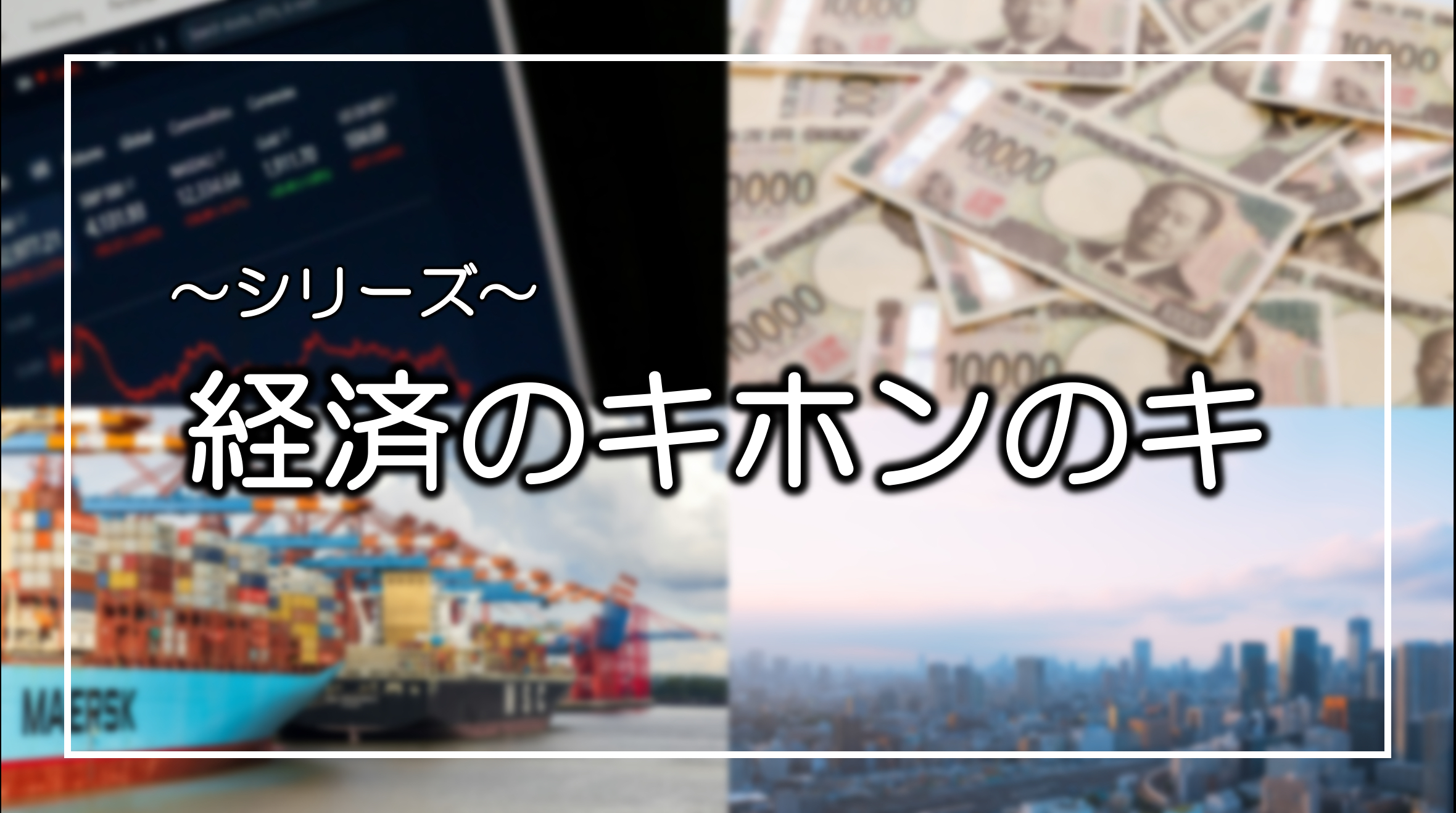「景気がいい」「景気が悪い」という言葉はニュースでよく耳にします。
日本では、いわゆるバブル景気の崩壊後に「失われた30年」という長期の不況に喘いできました。
では、「景気」とはそもそも何でしょうか?
この記事では、「景気」についてまとめてみます。
この記事のまとめ
- 「景気」とは、「経済活動の活発さ」を表す
- 景気はさまざまな指標で評価できる
- 景気を適度な範囲に収めることが、社会の安定に必要
1. 景気の定義
「景気」とは、簡単に言えば「経済活動の活発さ」を表す言葉です。
- 好景気(景気がよい、好況)
企業が利益を出しやすく、それに伴って人々の給料や雇用が安定して増える状態。
消費も活発になり、経済全体が勢いづきます。 - 不景気(景気が悪い、不況)
企業の売り上げや利益が落ち込み、給料や雇用が不安定になりやすい状態。
消費が落ち込み、経済が停滞します。
景気は波のように周期的に上下するのが特徴で、永遠に上り調子でも下り調子でもありません。
2. 景気を測る指標
景気の良し悪しを「なんとなくの雰囲気」ではなく、数字で判断するために使う代表的な指標がこちらです。
- GDP(国内総生産)
国内で一定期間に生み出されたモノやサービスの総額。
増えていれば景気は拡大、減っていれば縮小傾向とみなします。 - 失業率
働きたいのに職がない人の割合。景気が良ければ下がり、悪ければ上がります。 - 物価(消費者物価指数:CPIなど)
商品やサービスの値段の変動。
景気が良くなると物価が上がり(インフレ)、景気が悪くなると下がる(デフレ)傾向があります。
3. 景気がよいとき・悪いときに起こること
景気がよいとき

- 企業の売上増 → 賃金やボーナスが増える
- 賃金が増える
- 消費が活発になり、新しいビジネスが生まれやすい
- 急激に物価が上昇するリスクもある
景気が悪いとき
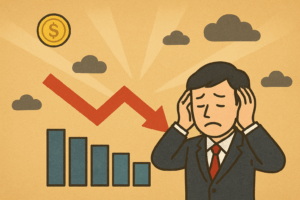
- 企業の売上減 → 賃金カットや雇用調整が行われやすい
- 求人が減る
- 消費が落ち込み、さらに企業の売り上げが減り・・・という悪循環に陥る
まとめ
景気は私たちの給料、仕事、さらに物価に直結する重要な「経済の体温」ともいえます。
体温のように、熱がありすぎても冷えすぎてもよくありません。適度な範囲内に収まっていることが社会が安定に不可欠です。
その適度な範囲内に収まるように調整するのが、「経済政策」の役割でもあります。
ニュースの「GDPが◯%成長」や「失業率が改善」という言葉の本質的な意味を知れば、世の中の動きがぐっと見えやすくなります。