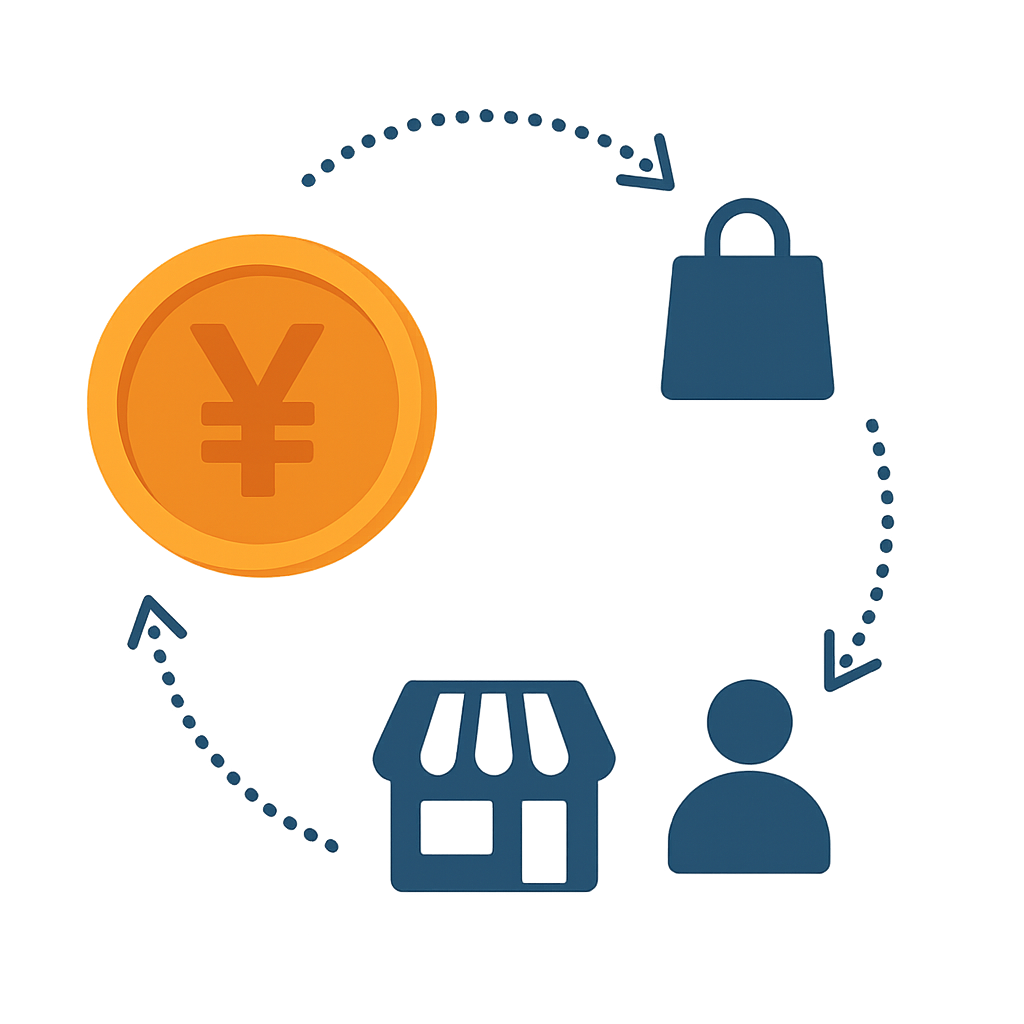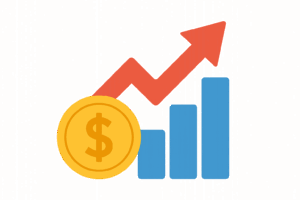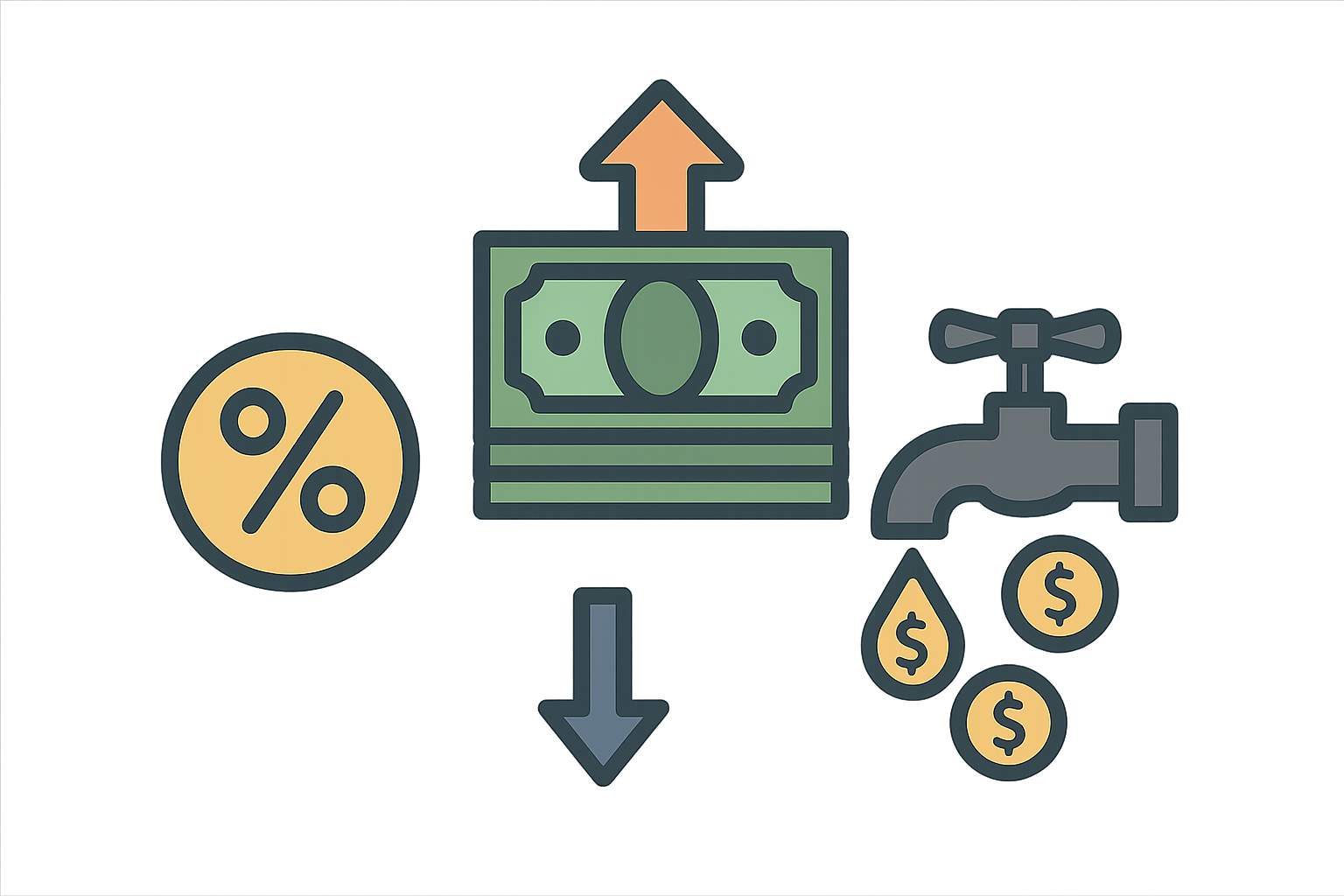前回の記事では「お金を増やせば景気が良くなる」という基本の仕組みを見ました。
同時に、「お金があっても動かないときがある」という例外についても触れました。
では、この「お金が動く・動かない」という現象をどう捉えればいいのでしょうか?
ここで登場するのが 「貨幣の速度」 という考え方です。
この記事のまとめ
- 貨幣の速度とは、「お金がどれくらい世の中を回っているか」を表す考え方
- 同じ1万円でも、回れば回るほど経済効果は大きくなる
- 景気の良し悪しを判断するには「お金の量」だけでなく「お金の動き方」にも注目する必要がある
貨幣の速度とは?
「貨幣の速度」とは、1枚のお金がどれくらい繰り返し使われるか を表す言葉です。
- 1万円を一度だけ使って財布にしまったら、経済に与える効果は1万円分。
- でも同じ1万円が、飲食店→仕入れ業者→運送会社→従業員の給料…と何度も回れば、経済全体にもっと大きな効果をもたらします。
つまり、同じお金でも「回る」ほど経済は元気になる のです。
貨幣の速度が落ちるとどうなる?
将来への不安が広がると、人々はお金を貯め込み、企業も投資を控えます。
これは、お金の量自体はあっても「回らない」=「貨幣の速度が落ちている」状態といえます。
これは、前回触れた「お金があっても景気が良くならない」現象の正体でもあります。
景気を見るもう一つの視点
経済を考えるとき、「お金の量」そのものに注目しがちです。
でも実際には、
- どれだけお金が社会にあるか(量)
- それがどれだけ動いているか(速度)
この2つが組み合わさって、はじめて景気の良し悪しが決まります。
だからこそ、景気を良くするためには「お金を増やす」だけでは足りず、
人々が安心してお金を使える環境をつくること が大切になるのです。
人々が安心してお金を使える環境とは?
貨幣の速度を高めるためには、人々が「安心してお金を使える」と感じられる社会環境を整えることが欠かせません。では、その安心感はどのように生まれるのでしょうか。
- 経済的な安心
- 安定した雇用や、将来にわたって持続可能な年金・医療制度があれば、過度に貯蓄に走らずにすむ
- 物価が安定していれば「今お金を使っても損をしない」という安心感につながる
- 公平な制度設計
- 税制や社会保障に偏りがあると「自分だけが損をしているのでは」という不公平感が広がり、財布のひもは固くなる
- 格差の是正や教育・子育てへの投資は、消費を促すだけでなく社会全体の安心感を高める
つまり、人々が将来を信じて行動できる環境が整って初めて、貨幣の速度は高まり、経済は持続的に成長していくのです。
まとめ
景気を動かすのは「お金の量」だけではありません。
同じお金でも、人から人へと繰り返し使われれば大きな経済効果を生みます。
逆に、お金が財布や銀行に眠ったままだと、どれだけ増やしても景気は動きません。
つまり大事なのは、「お金があるか」だけでなく「お金が回っているか」。
この2つの条件を整えてはじめて、経済は成長をはじめます。