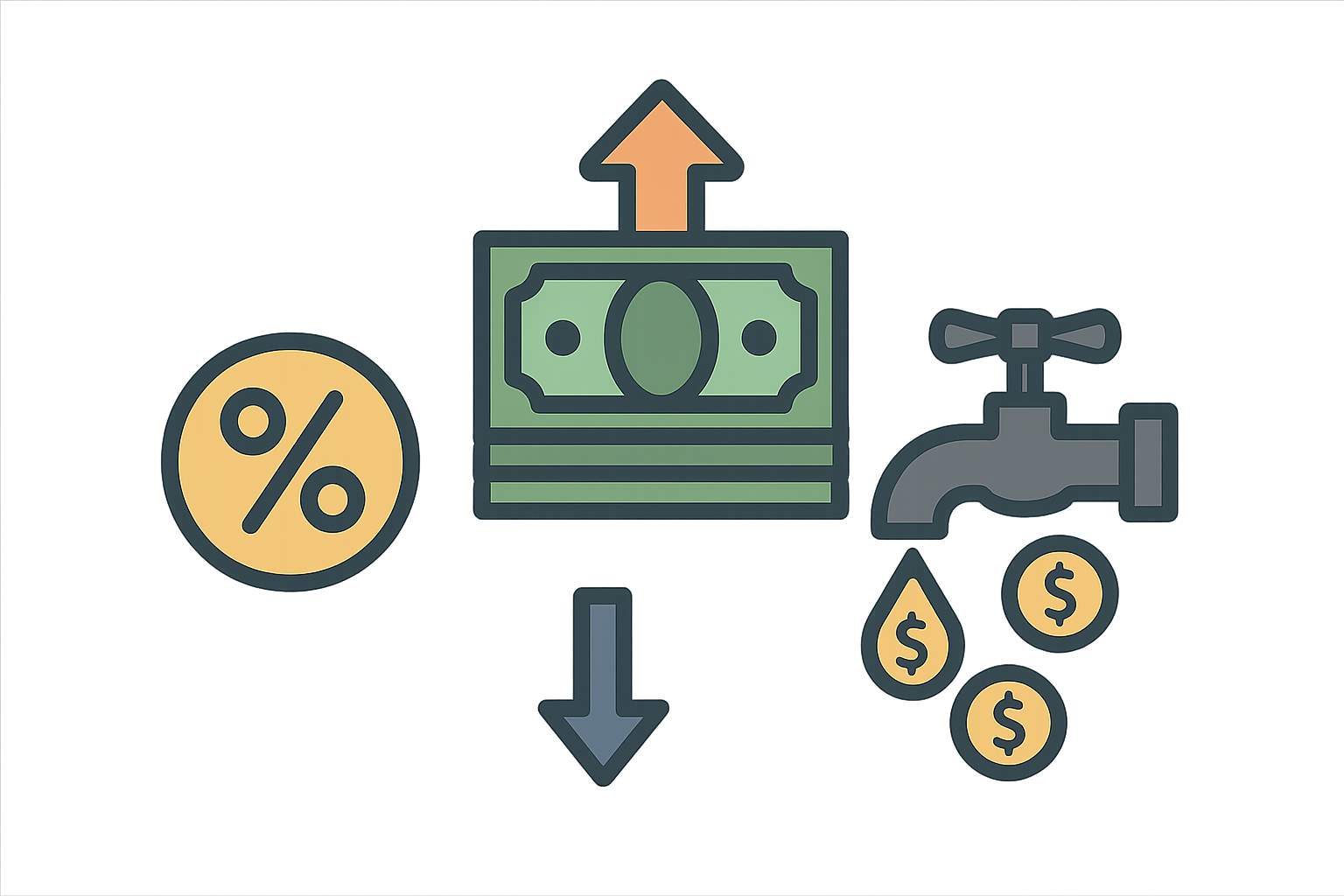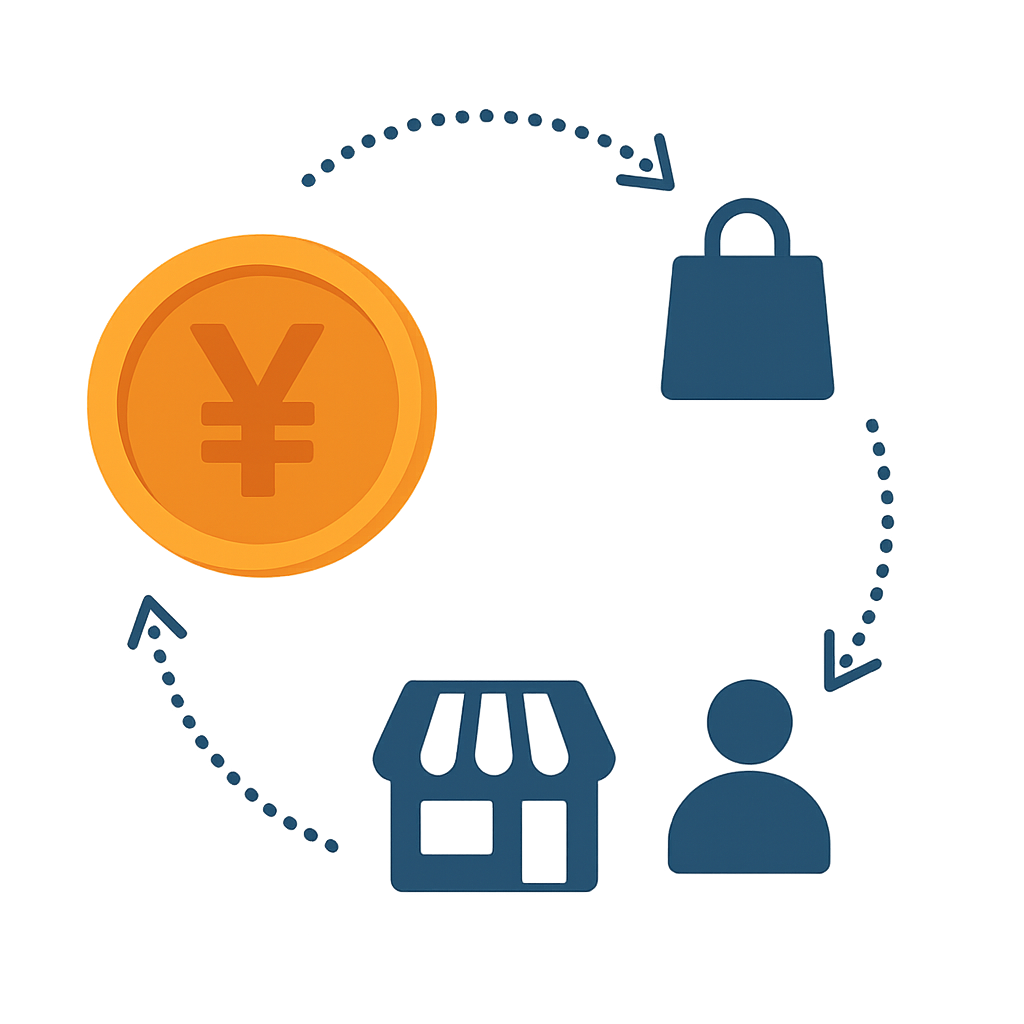ニュースで「日銀が金利を引き上げました」「金利が据え置かれました」といった言葉を耳にしたことはありませんか?
けれども、「金利が変わると自分の生活にどう関わるのか」「なぜそれが景気や物価に影響するのか」は、なかなかわかりにくいものです。
実は金利は、世の中に出回るお金の量を調整するスイッチのような役割を持っています。私たちが意識しなくても、ローンの返済額や預金の利息、さらには企業の投資活動や雇用環境にまで影響を及ぼしているのです。
この記事では、まず「そもそも金利とは何か」から出発し、金利が高いとき・低いときに世の中のお金の流れがどう変わるのか、さらに中央銀行がどのように金利を使って経済を安定させているのかを解説します。
- 「金利」とは、「お金を使うときにかかる手数料」
- 金利が低ければ借入や消費が増えて景気を刺激し、高ければ借入や消費が抑えられて景気を冷ます
- 中央銀行の役割は、景気が悪いとき金利を下げてお金を流しやすくし、過熱気味のとき金利を上げてお金の流れを抑えること
そもそも金利とは
金利とは、簡単にいうと「お金を使うときにかかる手数料」のことです。
- 銀行に預金をすると利息がつきますが、これは「お金を貸したことへの見返り」
- 住宅ローンや自動車ローンを借りると利息を払いますが、これは「お金を借りたことへの対価」
私たちがスーパーで買い物をするときに「モノの値段」があるのと同じように、「お金を使うこと」にも値段がついている―そう考えるとわかりやすいでしょう。
お金の「流れ」を決めるスイッチ
私たちの暮らしや企業活動には「お金の流れ」が欠かせません。
景気が良いときには人々がお金を使い、景気が悪いときには財布のひもが固くなる。
この「お金の流れ」をコントロールするために、中央銀行(日銀など)が使う代表的な道具が「金利」 です。
金利が低いとき:お金は世の中に出やすい
金利が低い場合、「お金を使うときの手数料は安い」ということなので、
- 企業は安く資金を借りられるので、投資や設備拡大をしやすい
- 家計も住宅ローンや自動車ローンを組みやすく、消費が増える
結果として「借りやすく、使いやすい」状態になり、世の中にお金が回りやすくなります。
これは景気を刺激する方向に働きます。
金利が高いとき:お金は出にくくなる
逆に金利が高いと、「お金を使うときの手数料が高い」ため、
- 借金の返済負担が重くなるので、新しい借入を控える
- 家計もローン金利が高いため、大きな買い物をためらう
- 投資家は銀行預金や債券の利息が魅力的になるので、お金を使わずに預けようとする
つまり「借りにくく、使いにくい」状態になり、世の中のお金の流れは抑えられます。
これは景気の過熱を抑える方向に働きます。
中央銀行の役割
日銀のような中央銀行は、この金利を調整することで 「お金の量の蛇口」を開けたり閉めたりしている と言えます。
- 不景気 → 金利を下げ、お金を流しやすくする
- インフレが行き過ぎているとき → 金利を上げ、お金の流れを抑える
このようにして、景気を安定させ、物価の急激な変動を防いでいます。
まとめ
金利は単なる数字ではなく、世の中のお金の流れを調整する重要なスイッチです。
私たちの生活で「ローンが安くなる」「預金の利息が増える」といった形で直接影響する一方、国全体の景気や物価をコントロールする大きな役割を担っています。
では、日銀はどうやって実際に金利を動かしているのか?
その仕組みについては、また別の記事でご紹介します。